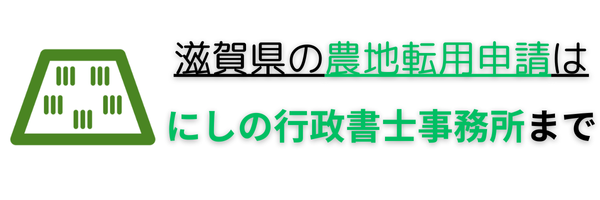農地転用の流れを徹底解説!手続きのポイントや注意点とは?

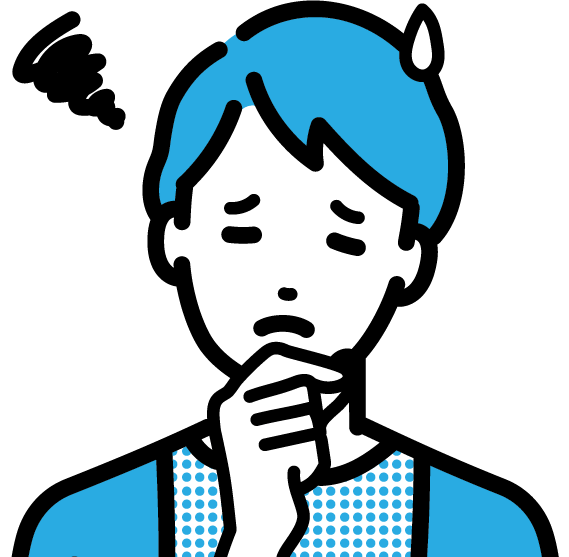
考えている人
農地転用の手続きってどうなっているんだろう…
調べてみたけど良く分からないし、必要書類も多い…

西野
農地転用の手続きや必要書類は、市町の農業委員会によって異なります。
法律の要件自体は全国共通ですが、具体的な手続きや必要書類にはローカルルールが存在します。
本コラムでは、農地転用の一般的な流れを解説します!
【注意】
農地転用の手続きは市町ごとにローカルルールが存在するので、必ず転用希望地を管轄する農業委員会の要綱を確認するようにしてください。農業委員会の要綱は、ホームページに掲載されていることが多いです(稀にホームページにも掲載されていないこともあります。その際は直接農業委員会に出向く必要があります。)。
この記事で分かること
- 農地転用の一般的な手続きが分かります
- 農地転用に必要な書類が分かります
- 農地転用にかかる費用の目安が分かります
- 無断転用(違法転用)した際のペナルティについて分かります
農地転用を検討する前に知っておきたい基礎知識
冒頭でも申し上げたように、農地転用の手続きはローカルルールが存在します。
しかし、農地転用は農地法という法律に基づいて行われるので、全国で共通する部分もあります。
本コラムでは、全国で共通する部分を解説していきたいと思います。
農地転用とは?

農地転用は、農地として指定されている土地(登記簿謄本の地目が「田」や「畑」など)を農業以外の目的(住宅地や商業地、工場用地など)で利用する場合に必要となります。
※農地を農地以外の用途で利用することを「転用」といいます。
日本では、農地法という法律によって農地の保護が重視されており、無計画な開発による食料生産基盤の崩壊を防ぐため、農地の転用には厳しい規制があります。
そのため、農地を他の用途で利用するには、農地法に基づいた申請や届出が必要です。
農地転用手続きは、特に都市部やその周辺で土地の有効活用を考える際に必要になることが多く、住宅、商業施設の建設や太陽光発電設備の設置を目的とした転用のほか、公共事業や社会資本整備に伴う転用も行われる場合もあります。
農地転用が必要になる具体的なケース
農地転用が必要になる具体的な状況には、次のようなものがあります。
- 住宅や建物の建設
農地を住宅地に変更する場合、農地転用が必須です。たとえば、農地に新しく家を建てたいと考えている場合、その土地が農地であれば転用の手続きが必要になります。 - 商業施設や工場の建設
商業用の店舗や工場を建設するために農地を利用したい場合も、農地転用を申請する必要があります。特に都市の拡大に伴って、農地の商業地転用がよく見られます。 - 公共インフラの整備
道路や鉄道、学校、病院などの公共施設を建設するために、農地を転用することがあります。こうした転用は、地域住民の生活基盤を整えるために行われることが多く、場合によっては早急な対応が求められます。 - 農業の廃業や跡地の活用
高齢化や後継者不足により、農業を続けられなくなった場合、農地を転用して活用するケースもあります。農業を辞めることを前提に、その土地を転用して住宅や施設に活用するのは一つの選択肢です。

農地転用の手続きと流れ
農地転用を行うためには、いくつかのステップを踏んで申請手続きを進める必要があります。
ここでは、具体的な手続きの流れと重要なポイントを解説します。
ステップ1:まずは市区町村役場や農業委員会に相談
農地転用の手続きを始める前に、まず最初に行うべきことは、農地がある市町の市区町村役場や農業委員会に相談することです。
農地の中には転用が困難な農地が存在します。また、転用するに際して、農地法以外の規制法令や市町の条例が存在します。
こういったことを役所や農業委員会に照会し、どのような手続きが必要か確認します。
さらに、農地が市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるかで手続きの難易度や要件が変わります。
ポイント
- 事前相談では、土地の現況や転用後の用途を明確に伝えることが必要です。
- 転用が認められない場合や、制約が厳しい地域もあるため、早めに確認しましょう。
- 相談時に必要な書類や資料を事前に用意するとスムーズです。

西野
農業委員会を訪問する前に「農地の登記簿謄本」と「公図」と「位置図」を用意しておきましょう。
登記と公図は法務局で取得できます。位置図は、農地の位置がどこにあるか分かるものであれば何でも構いません。
これらを揃えてから、農業委員会へ相談に行くようにしましょう。
『土地利用計画図』があると、更に話が早いです。
ステップ2:必要書類の準備
市区町村役所や農業委員会に相談した後は、農地転用の申請に必要な書類を準備します。
手続きには複数の書類が必要となり、これらを正確に揃えることでスムーズに申請を行うことが可能です。
以下は、一般的に必要とされる書類の一覧です(あくまで参考までに)。
必要書類リスト
- 農地転用許可申請書
申請する内容や転用する農地の詳細を記載します。 - 土地登記簿謄本
対象の農地の登記情報を示す書類です。法務局で取得できます。 - 公図
申請予定地とその周辺の筆界を示す地図です。法務局で取得できます。 - 転用後の計画図面
転用後の具体的な利用計画を図面で示す必要があります。 - 造成計画と断面図・横断図
農地に関連する税金が適切に納められているかを証明する書類です。 - 排水計画
転用の目的にもよりますが、排水が発生する場合、どのように処理するのか、その計画の提出を求められます。 - 建物・工作物の構造図・平面図・断面図など
転用地に建築物や工作物を設置する場合必要となります。 - その他、自治体によって指定された書類

ポイント
- 不足や不備があると申請が遅れるため、書類は漏れなく準備しましょう。
- 自分で書類を整えるのが難しい場合は、専門家に依頼することを検討すると良いでしょう。

西野
申請受付窓口の農業委員会事務局が必要書類を案内してくれます。
転用目的や、各市町ごとに準備する書類が微妙に異なるため、事前の相談が欠かせません。
転用目的や工事の施行態様に応じて、必要な手続きを全て確認しておく必要があり、各担当窓口まで相談に行かなければなりません。
結構大変ですが、見落とすと許可取得時期が大きくズレる恐れがありますので、徹底的に調査しておきましょう。
ステップ3:申請書類の提出と審査の流れ
書類が揃ったら、農業委員会事務局に書類を提出します。
提出後、提出された書類をもとに審査が行われます。
審査では、以下のような点が確認されます。
- 転用の目的や利用計画が農地法に適合しているか
農地の保護を目的とする法律が守られているかどうか、転用後の用途が妥当であるかがチェックされます。 - 土地の利用が地域の計画と一致しているか
都市計画など地域全体の開発方針に合致しているかも重要な判断基準です。 - 農業生産に対する影響
周辺の農業への影響や、地域の農業振興計画に影響を与えないかが確認されます。
審査期間の目安:
申請から許可が下りるまでの期間は地域によって異なりますが、一般的には1~3ヶ月程度かかることが多いです。
滋賀県の場合、特に問題がなければ、申請後40日前後で許可が下りることが多いです。

西野
農地転用の「申請」ですが、各市町農業委員会事務局が毎月「案件締日」を設けており、この締日に申請が間に合わない場合、自動的に翌月の申請扱いとなります。
工期が決まっていたりする案件では、間に合わないと自動的に1ヵ月遅れることになります。
※「届出」の場合はいつでも受け付けてもらえます。
たまに案件締日の前日になっても書類を提出して下さらない事業者様がいらっしゃるので、こういう時はヒリつきますよ!
ステップ4:農地転用許可証の取得
審査に通過すると、農地転用の許可証が発行されます。この許可証を受け取ることで、農地を転用しての工事や開発を正式に開始することができます。
許可取得後に可能となる作業
- 許可証を取得した後は、転用後の計画に従って建築や開発が進められます。住宅や商業施設の建設が開始可能です。
- 許可が下りた段階で、土地の用途は農地から転用先の用途に変更されたとみなされます。そのため、建設に伴う関連する手続きもこの段階で進めることができます。
次に進めるステップ
- 許可後、速やかに着工しない場合、許可が失効することがあります。計画に基づき、着工や工事を進めましょう。
- また、転用後の土地利用に変更がある場合は、再度申請(変更申請)が必要となる場合があります。

西野
少し細かいですが、申請してからどういった内部処理が行われているのか解説します。
①申請→②担当者が農業委員総会の招集→③翌月10日に総会開催→④総会で転用申請が許可相当か否か決議→⑤許可相当の場合、許可証が発行
申請後は上記流れを辿ることになります。
農業委員を総会に招集する必要があるため、毎月案件締め日が設けられているのだと思われます。
また、許可相当と判断されてから許可用の発行まではそれ程時間が掛かりません。
農地転用に関する注意点とよくある質問
農地転用には複雑な手続きが伴い、慎重に進める必要があります。
ここでは、農地転用に関する費用や税金、無許可転用のリスクについて、よくある質問を交えながら詳しく解説します。
農地転用にかかる費用や手数料
農地転用を行う際には、申請に関して専門家に支払う費用が発生しますが、これらは地域や土地の状況によって異なります。
主な費用内訳
- 測量費用
転用を行う土地の面積を正確に把握するための測量が必要になる場合があります。測量費用は土地の広さや地形の複雑さによって異なり、数十万円以上になることもあります。 - 行政書士への依頼費用
専門家に書類の作成や手続きを依頼する場合、その報酬として費用がかかります。行政書士に依頼する場合の相場は、5条申請で8万円~10万円のようです。
弊所の料金体系はコチラをご覧ください。 - その他の費用
転用する土地に応じて、現地調査や都市計画に関する調査費用が発生する場合があります。また、申請が許可された後も、建築確認申請や工事開始のための費用が別途かかる場合があります。
地域による違い
農地転用にかかる費用は、地域によって異なります。
都市部では手続きが厳格であるため、費用が高くなる傾向があります。
農業が盛んな地域では、農地保護の観点から転用が認められにくく、さらに時間とコストがかかる場合もあります。
転用後に発生する税金や費用の増加
農地を転用することで、土地の用途が変わると、税金の負担も大きく変わります。
特に、固定資産税が大きく増加する可能性があります。事前に確認しておくと良いでしょう。
固定資産税の変動
農地は、農業を継続する目的で利用される土地に対して優遇税制が適用されています。
そのため、農地としての税率は非常に低く抑えられています。
しかし、転用後に土地の用途が住宅地や商業地となると、固定資産税の評価額が一気に引き上げられ、税金が数倍に増加することがあります。
たとえば、同じ面積の土地でも、農地のときは数千円の税金だったものが、住宅地や商業地に転用すると数万円、あるいは数十万円に増加することがあります。
これに加え、都市計画税なども課されることがあるため、転用後の税負担をしっかり把握しておくことが重要です。
その他の費用
転用後に発生する税金以外の費用として、開発費やインフラ整備に関連するコストが必要になることもあります。
たとえば、上下水道や電気、ガスなどのインフラが整備されていない農地を住宅地にする場合、これらの工事費用が大きな負担となることもあります。
無許可で転用した場合のリスク
農地を無許可で転用してしまうと、罰則を科されてしまいますので注意が必要です。
行政から違反是正命令を打たれたり、罰則を科されてしまうと、多大な損害を被るだけでなく社会的信用も失ってしまいかねません。
お金がかかる面倒な手続きでも、きちんと行っておくことが重要です。
主なリスク
- 原状回復命令
無許可で農地を転用した場合、行政から土地を元の農地の状態に戻すよう命じられることがあります。
これには大きな費用と時間がかかるため、結果的に転用が失敗に終わる可能性が高いです。 - 罰則・罰金
無許可転用は農地法違反に該当し、個人や法人には罰金や罰則が科されることがあります。
罰金は数十万円から数百万円に上ることがあり、重大な経済的負担となる可能性があります。 - 売買や融資の制約
無許可転用が行われた土地は、売買や融資を受ける際に問題となることがあります。
土地の法的な問題が未解決であるため、買い手がつかない、あるいは金融機関から融資が下りないという事態が発生します。
結論として…
無許可で農地転用を行うことは、多大なリスクを伴うため、絶対に避けるべきです。
もし農地転用を考えている場合は、必ず事前に許可を取得し、法的な手続きを正しく踏むことが重要です。
農地転用をスムーズに進めるためのポイント
農地転用を円滑に進めるためには、事前の準備や適切なサポートを得ることが重要です。
ここでは、事前調査の必要性と専門家に依頼するメリットについて詳しく解説します。
事前調査をしっかり行うことの重要性
農地転用をスムーズに進めるためには、まず対象となる農地の現状や法的な制約を正確に把握することが不可欠です。
事前調査を怠ると、申請後に問題が発覚し、手続きが大幅に遅れたり、場合によっては申請が却下されたりすることもあります。
以下に、調査すべきポイントとその方法を紹介します。
1. 農地の位置と用途地域の確認
- まず、転用を考えている農地がどの用途地域に属しているかを確認しましょう。市街化区域や市街化調整区域では転用の難易度が大きく異なります。市街化区域内の農地は比較的転用が許可されやすいですが、市街化調整区域では規制が厳しく、農地として保護される傾向があります。
- 自治体の都市計画課や農業委員会で用途地域を確認することが可能です。
2. 農地の形質や地理的条件の把握
- 農地の面積、形状、周辺の状況を確認することも重要です。例えば、地盤が弱い土地や洪水リスクが高い地域では、転用後の建築計画に支障が出る可能性があります。
- 地図や現地調査を通じて、土地の地理的条件や周辺のインフラ(道路や公共施設の整備状況)もチェックしておくとよいでしょう。
3. 土地所有者や権利関係の確認
- 土地が共有名義になっている場合や抵当権が設定されている場合、手続きが複雑化する可能性があります。所有者や権利関係を法務局で確認し、問題がないかどうかを調査しておくことが大切です。
4. 農地の特性に基づく法的制約の確認
- 転用を進める際には、土地の特性に応じた法的制約(農業振興地域制度、開発許可制度など)があるかどうかも調査する必要があります。特に農業振興地域内の農地は、原則として転用が認められないため、事前に確認しましょう。
事前調査のポイント
- 現地調査だけでなく、法務局や自治体へのヒアリングも欠かせません。
- 調査をしっかり行うことで、後から手続きが滞るリスクを軽減できます。
専門家に依頼するメリット
農地転用は法的な手続きが複雑であり、多くの書類や手続きが必要です。
こうした手続きを自分で進めるのは大変な負担になることが多いため、専門家である行政書士に依頼することは非常に有効な方法です。
1. スムーズな手続きの進行
- 行政書士は、農地転用の手続きに精通しており、必要な書類の作成から申請までを一貫してサポートしてもらえます。書類不備や手続きのミスによる遅延を防ぐことができ、迅速な手続きが期待できます。
- また、各自治体や農業委員会との連携がスムーズに行えるため、地元の規制や要件に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
2. 複雑な書類作成の代行
- 農地転用には、多くの書類や資料が必要で、内容の不備や誤記入があると申請が遅れるだけでなく、却下される可能性もあります。専門家に依頼することで、正確かつ適切に書類が作成され、無駄な手戻りを防ぐことができます。
- 特に、申請書類には法的な知識が求められる場合が多いため、専門家の知識が役立ちます。
3. 法的リスクの軽減
- 転用申請には、土地の法的な問題や所有権の確認など、さまざまなリスクが伴います。行政書士に依頼することで、土地に関する法的なリスクを事前に把握し、問題が発生しないように手続きを進めることができます。
- また、無許可転用のリスクを避けるためにも、行政書士による適切なアドバイスが有効です。
4. 時間と労力の節約
- 農地転用の手続きは、複数の機関を訪れたり、何度も書類を確認したりする必要があります。専門家に依頼することで、これらの煩雑な手続きに時間を割く必要がなくなり、他の重要な業務に集中することができます。
専門家に依頼する際のポイント
- 農地転用の経験が豊富な行政書士を選ぶことが重要です。地域の規制や条件に精通している専門家であれば、より的確なアドバイスを受けることができます。
- 費用については、依頼内容や地域によって異なりますが、事前に見積もりを確認し、納得のいく形で契約することが大切です。
まとめ
- 農地転用は農地法に基づく手続きであり、全国共通のルールがある一方で、市町村ごとのローカルルールも存在する。
- 農地転用とは、農地(田・畑など)を農業以外の目的で利用することで、住宅地や商業施設、工場、太陽光発電などに活用する場合に必要。
- 農地転用が必要な具体例には、住宅や商業施設の建設、公共インフラ整備、農業廃業後の跡地利用などがある。
- 手続きのステップは①市町村役場・農業委員会への相談 → ②必要書類準備 → ③申請・審査 → ④許可証取得の流れ。
- 必要書類には申請書、登記簿謄本、公図、計画図面、造成計画、排水計画、建物図面などがあり、不備があると手続きが遅れる。
- 審査では農地法との適合性、地域計画との整合性、農業生産への影響などが確認され、許可までに1〜3か月程度かかる(滋賀県は約40日前後)。
- 費用面では測量費用、行政書士への依頼費用(8〜10万円程度)、調査費用などが発生し、地域によって差がある。
- 税金面では固定資産税が大幅に増加する可能性があり、転用後は都市計画税やインフラ整備費も加わる場合がある。
- 無許可転用のリスクは原状回復命令、罰金(数十万〜数百万円)、売買や融資の制約などがあり、必ず事前に許可を得る必要がある。
- スムーズに進めるポイントは事前調査(用途地域・土地条件・権利関係・法的制約の確認)と、行政書士など専門家への依頼であり、時間・労力・リスク軽減につながる。
農地転用は、専門の行政書士に依頼することで大幅にスムーズになり、無駄な時間や費用を防ぐことができます。
当事務所は、滋賀県内の多数の案件をサポートしてきた実績があり、滋賀県内の地域ごとのルールにも精通しています。
農地転用をご検討中の方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
お客様の状況に合わせた具体的なアドバイスをご提供いたします。
〈お気軽にご相談ください〉
※LINEからのお問合せ・ご相談がスムーズに進むのでお勧めです。