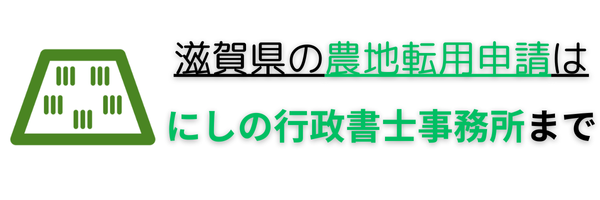【滋賀県】市街化調整区域の農地転用条件を徹底解説!許可基準・手続き・例外ケースまで完全ガイド
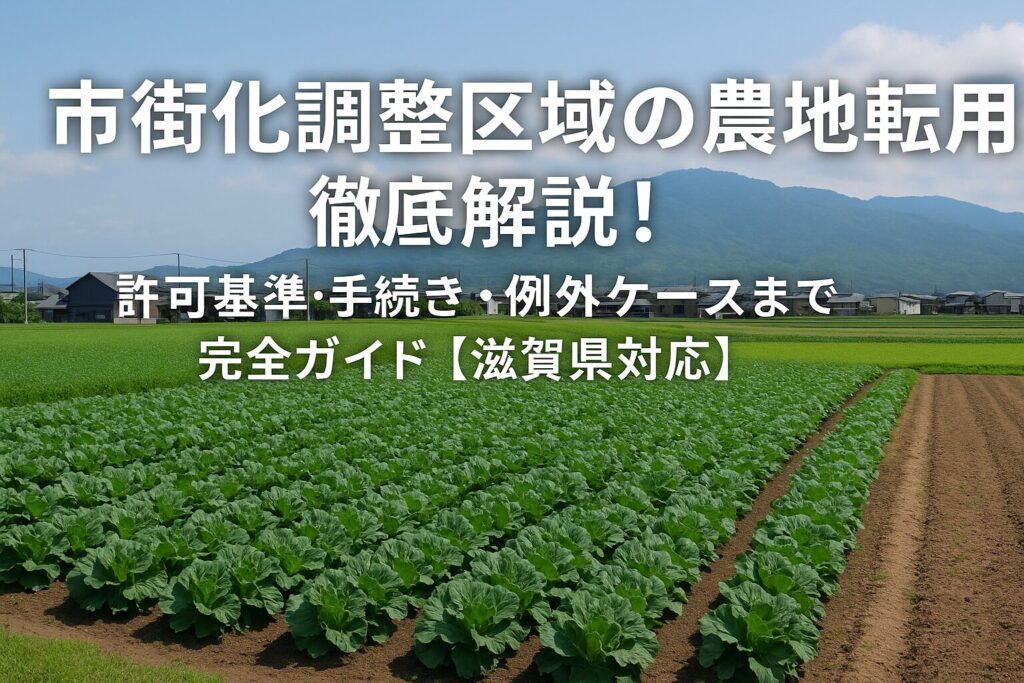
市街化調整区域の農地転用は、市街化区域や農用地区域の転用よりも条件が厳しく、専門知識が必要です。
「自宅を建てたい」「事業用地にしたい」「売却したい」など、目的は人それぞれですが、許可が下りるかどうかは土地の区分や利用計画によって大きく異なります。
本記事では、農地転用申請に特化した行政書士が、許可基準から申請手続き、例外規定、滋賀県での実務ポイントまで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
市街化調整区域と農地転用の基礎知識
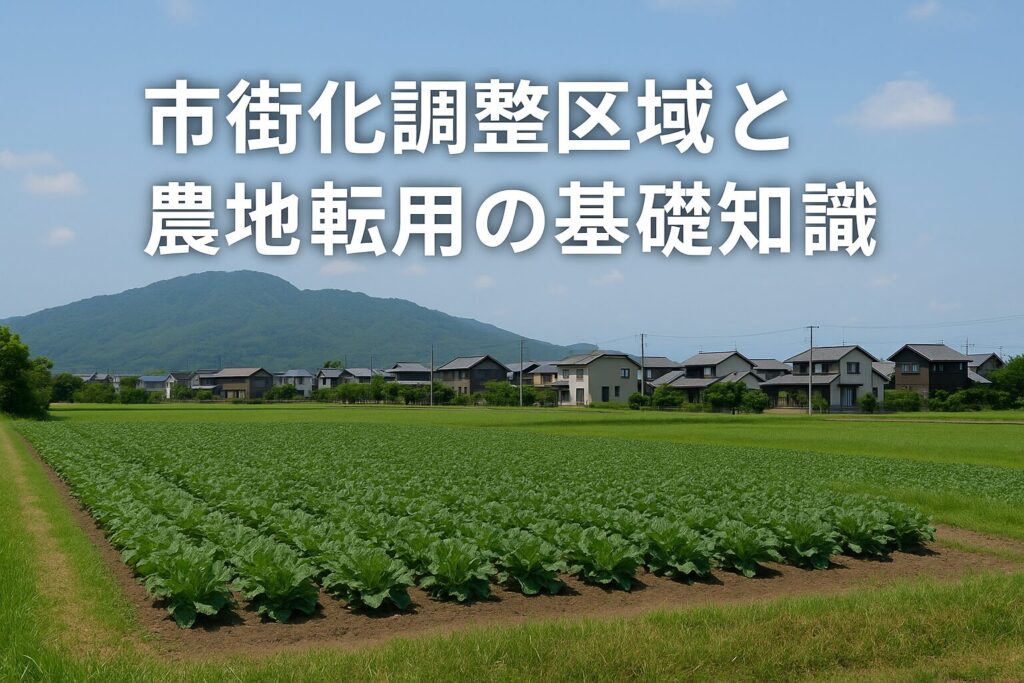
市街化調整区域での農地転用は、他の区域に比べて制限が厳しく、手続きも複雑です。
まずは、この区域の都市計画法上の位置づけや目的を理解し、農地法との関係性を押さえることが重要です。
ここでは、市街化調整区域の特徴と農地転用の基本的な仕組み、そして転用を行う際に必要となる法的手続きをわかりやすく解説します。
市街化調整区域とは?都市計画法上の位置づけと特徴
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制する区域」として定められたエリアで、無秩序な都市拡大を防ぎ、農業や自然環境を守る目的があります。
滋賀県では琵琶湖を囲むように広がる農村地域や湖岸地帯が多く指定されており、特に近江八幡市、守山市、長浜市などでは、市街化区域に隣接する一帯が調整区域になっています。
この区域では、原則として新たな住宅や商業施設の建築は認められず、農業や森林利用などの現状維持が求められます。
ただし、都市計画法第34条の例外規定に該当する場合には、一定の条件で開発や建築が許可されることがあります。
その代表例が「農家の分家住宅」で、本家の子や孫が農業を継ぎながら居住するための住宅建築は条件付きで認められます。
滋賀県特有の特徴として、琵琶湖総合開発以降、環境保全への意識が高まり、農地転用に際して景観・水質保全条例の審査が並行して行われています。
たとえば大津市や草津市の湖岸地域では、外壁の色彩や建物高さに制限があり、農地法だけでなく景観条例の要件もクリアしなければなりません。
にしの行政書士事務所では、こうした複合的規制を考慮し、申請前の段階で農地法・都市計画法・景観条例の3つを同時にチェックします。
これにより、後から設計変更を求められるリスクを最小限に抑えています。
農地転用とは?農地法と都市計画法の関係
農地転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置場、太陽光発電所など農業以外の用途に変更することを指します。これを行うには、農地法による許可が必要です。
- 農地法第4条許可:自己所有の農地を自己で転用する場合
- 農地法第5条許可:農地を売却または貸して、他者が転用する場合
農地法許可に加えて、転用目的(計画)によっては、市街化調整区域の場合は都市計画法第29条の「開発許可」も必要になることが多く、二重の許可取得が必要になります。
例えば、市街化調整区域の農地に倉庫を建てる計画では、農地法の転用許可と都市計画法の開発許可を同時に進めなければなりません。
さらに、転用目的(計画)によっては環境影響評価や景観条例の審査も必要です。
例えば、長浜市は市全域が景観条例の対象区域となっており、建築物の高さ・面積によっては景観条例に基づく届出が必要になります。

農地転用をスムーズに行うためには、関係諸法令の入念な事前調査が欠かせません。
実際、申請業務に携わる中で、農地転用だけで済むケースは少ないと実感します。
必要な手続きを見落としていた場合、農地転用の許可は下りません。
開発許可、景観条例、砂防法、河川法など様々な法令の手続きを徹底的に調査する必要があります。
農地転用の許可基準とできないケース

農地転用の可否は、土地の「農地区分」や立地条件、利用目的によって大きく変わります。
特に市街化調整区域では、一定の基準を満たさない限り許可が下りません。
ここでは、各農地区分ごとの許可可否の傾向や、許可が得られない主な理由を整理し、事前に計画を立てる際に役立つ情報を提供します。
不許可リスクを避けるためのポイントもあわせて解説します。
農地区分ごとの許可可否一覧表
農地転用可否は、「農地区分」によって大きく左右されます。農地区分とは、農地の地力や立地条件に基づいて分類されるもので、主に次のように区分されます。
| 農地区分 | 特徴 | 許可可否の傾向(滋賀県) |
|---|---|---|
| 第1種農地 | 高い地力を持ち、大規模営農に適する | 原則不許可(例外極少) |
| 第2種農地 | 比較的条件の良い農地 | 条件付き許可 |
| 第3種農地 | 農業適性が低い | 原則許可 |
| 農用地区域内農地(青地) | 農業振興地域内で計画的に保全される農地 | 原則不許可 |
滋賀県では、近江八幡市や守山市の湖岸地域は第1種農地や農用地区域が多く指定され、これらは原則として転用が認められません。
逆に、大津市や湖南市の一部の丘陵地や市街化区域に隣接する第3種農地では、転用が比較的スムーズに進むことがあります。
また、滋賀県の特徴として、同じ農地区分でも「景観保全区域」や「環境保全型農業推進地域」に該当すると、許可が厳しくなる傾向があります。
たとえば、長浜市木之本町の一部地域では、湖西の景観保全方針により、第3種農地であっても事業用途による転用が認められないケースがありました。
にしの行政書士事務所では、申請前に必ず農業委員会で農地区分の確認を行い、さらに市町ごとの独自制限の有無も調査します。これにより、許可見込みを事前に把握し、土地活用計画を修正することで、不許可リスクを最小限に抑えています。

「農地区分」は、分かりやすく言うと、「農地のランク」のようなものです。
農地としてランクが高い土地は、原則として転用ができません。
繰り返しになりますが、どんな転用目的にせよ、事前に調査することが大切です。
ある程度計画が進んでから、実は転用予定地が「第1種農地」だった、なんてことになっては目も当てられません。
なお、農地区分には他にも「甲種」というものがありますが、「第1種」と同じく、優良農地として原則転用はできません。
農地転用が不許可になる主な理由
一般的に農地転用が不許可になる理由は、大きく分けて次の4つです。
- 農業振興地域内農用地区域(青地)である
農用地区域は農業生産を維持するために厳格に保護されており、住宅や事業用地への転用は原則認められません。
近江八幡市の農業地帯では、この理由による不許可が多く見られるようです。 - 周辺農業や景観への悪影響
たとえば湖西地域や琵琶湖岸では、太陽光発電施設が景観や観光資源への影響を理由に認められないケースがあります。
草津市では、観光道路沿いの農地転用申請が景観条例に抵触し、不許可となった事例があったようです。 - 利用目的の不明確さや虚偽申請
実際には資材置場として使用する予定なのに住宅と申請した場合など、虚偽や不明瞭な申請は即座に不許可となります。 - 書類不備・計画の具体性不足
書類の提出先は、市町の農業委員会事務局ですが、事務局毎に求められる書類の水準が異なります。
中には審査が厳しい農業委員会もありますので、書類審査の段階で落とされてしまうことがあります。
また、転用計画を実現するだけの資金や融資証明書などが準備できていないと、「計画実現の確実性なし」と判断され、申請を受け付けてもらえません。
不許可理由は法律の条文だけでなく、地域の運用や行政判断によっても変わります。
特に滋賀県では「地域農業や景観保全との調和」が強く意識されており、これを軽視した計画は認められにくい傾向があります。
申請前に地域の事情を把握し、計画段階で配慮を盛り込むことが重要です。

農地転用の申請は、農業委員会事務局毎に求められる手続き・書類が異なるので、本当に大変です。
湖北の5条の転用依頼が多いですが、長浜市の農地転用は個人的にやりやすいですね。長浜市は担当の方と仲良しというのもありますが。
反対に米原市の農地転用はやりづらいと感じます。米原市の農業委員会事務局は厳しいですね…
市街化調整区域の農地を売る・活用する方法

市街化調整区域の農地を売却・活用する場合、農地法や関係諸法令の制限をクリアする必要があります。
売却先が農家か非農家か、活用方法が資材置場か駐車場かなどによって、必要な許可や条件が異なります。
ここでは、売却時に押さえておくべき手続きや契約上の注意点、許可が下りやすい活用事例など、実務で役立つ情報を詳しく紹介します。
農地を売るために必要な許可と手続き
農地を売却する場合、売却先が農家か非農家かによって必要な許可が異なります。
- 農地法第3条許可:農地を農地として農家に売る場合
- 農地法第5条許可:農地を非農家や法人に売却し、農地以外に転用する場合
市街化調整区域の場合、非農家への売却は許可が非常に難しく、特に第1種農地や農用地区域ではほぼ認められません。
一方、第3種農地や市街化区域に隣接する農地は、用途や立地によっては許可が下りる可能性があります。
売却前に農業委員会と事前協議を行い、許可見込みを確認することが重要です。
また、土地売買契約書には「許可取得を停止条件とする条項」を入れることが推奨されます。
これにより、許可が下りなかった場合に契約が自動的に白紙となり、売主・買主双方のリスクを軽減できます。

青地や第1種・甲種農地の転用は、無理だと思っておいた方が賢明です。
まず無理なので、そのことを頭に入れた上で、土地の選定を行うことをおススメします。
以前に青地の転用依頼が来て、農政課に相談し、何とか除外して貰えるように粘りましたが、普通に無理でした。
農地を活用する方法
市街化調整区域の農地は、売却が難しい場合でも、用途によっては転用して活用できます。代表的な例として以下があります。
| 活用方法 | 必要許可 | 滋賀県での特徴 |
|---|---|---|
| 資材置場 | 農地法第4・5条許可 | 周辺農地や道路状況への影響が審査対象 |
| 駐車場 | 農地法第4・5条許可 | 恒久舗装は景観・排水の観点から制限あり |
| 太陽光発電 | 農地法第4・5条許可+都市計画法許可 | 湖岸や景観区域では厳しい制限 |
特に太陽光発電は、滋賀県では景観保全条例や水質保全の観点から、パネル配置・色調・反射率の制限が厳しく、市町ごとに独自の条例を定めていることがあります。
例えば、『高島市開発指導要綱』(高島市)、『甲賀市みんなのまちを守り育てる条例』(甲賀市)、『米原市太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例』(米原市)など、市町独自に条例を設けており、農地転用とは別に申請を行う必要があります。
資材置場の場合も、近隣道路の幅員や通行車両の頻度、騒音・粉じん対策が審査対象となります。
駐車場活用は比較的許可が下りやすいですが、舗装方法や排水計画によっては景観や水質への影響を理由に修正を求められることがあります。
こうした点を踏まえ、用途ごとの条件を事前に確認することが、調整区域での活用成功の鍵となります。

条例の手続きは、本当にめんどくさ… 本当に大変です。
何だったら農地転用の申請より大変だったりします。
特に太陽光発電設備の設置目的の場合は、全国的に管理体制などが問題視されていることから、規制が厳しいです。
あと、滋賀県は琵琶湖があるからなのか、排水関係に関してもの凄く言われます。
その辺りも念頭に置いて、図面等を作成する必要がありますね。
農地転用の申請手続き
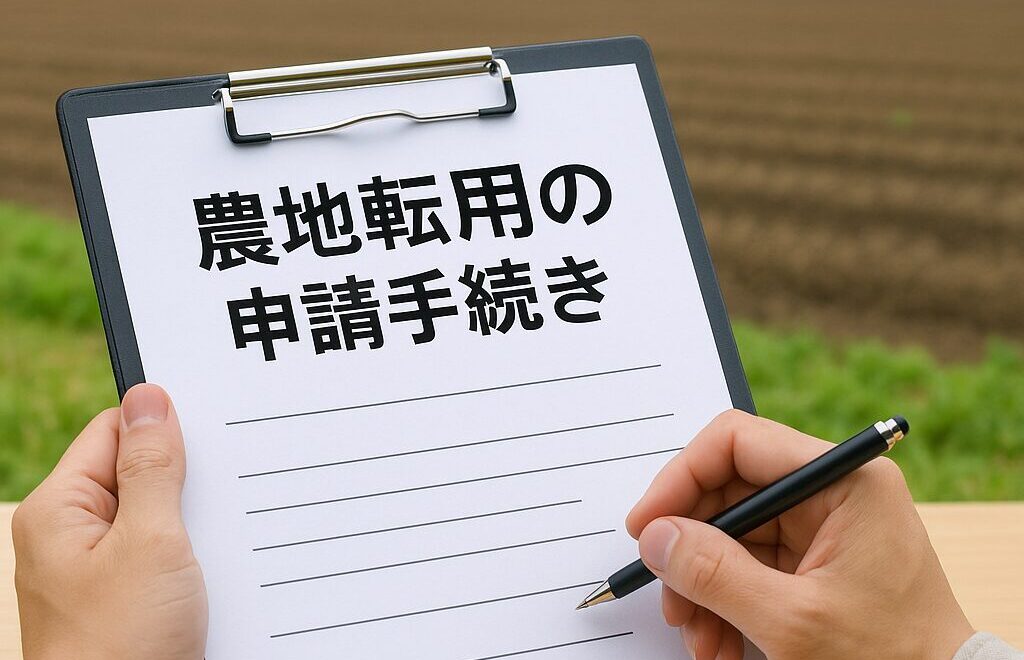
農地転用の申請は、事前相談から書類作成、現地調査、許可取得まで複数のステップを経て行われます。
ここでは、申請から許可取得までの流れと必要書類、そして3年ルールの意味や例外的な延長事例など、スケジュール管理の参考になる情報をまとめます。
農地転用申請のステップと必要書類一覧
農地転用申請は、以下の流れで進めるのが一般的です。
①事前相談(農業委員会・その他部署)
市町ごとの農業委員会に計画概要を説明します。許可の見込みがあるのか早期に確認してしまいます。
また、転用目的や工事の態様により異なりますが、農地転用の他に必要な手続きがないか確認します。
例えば、条例手続きの要否、重機の回送のために水路を占用するなら道路法の許可が必要ですし、河川が近くにあるなら工事が河川保全区域内の制限行為にあたる可能性があります。
他にもたくさんありますが、そういったことを全て調べる必要があります。
②必要書類の準備(市町や転用目的に応じて若干ことなります)
- 農地転用許可申請書
- 転用事由詳細説明書
- 法人登記簿謄本(申請人が法人の場合)
- 土地登記簿謄本
- 位置図・公図(写し)
- 現況写真
- 土地利用計画図(配置図・断面図など)
- 利用目的を示す契約書案や事業計画書
など、他にもまだまだたくさんあります。
詳細は各市町の農業委員会事務局のHPをご覧ください。
③申請書提出
農業委員会に提出し、審査を経て県知事または市長の許可を受けます。
審査はおおむね1〜2か月ですが、都市計画法の開発許可を伴う場合はさらに時間がかかります。
④現地調査・補正対応
現地の利用状況や周辺環境を確認され、不備があれば補正を求められます。にしの行政書士事務所では、事前に現地調査を行い、補正リスクを最小化しています。
⑤許可通知・許可証交付
「届出」ではなく「申請」の場合、各市町の農業委員会毎に「案件締め日」というのが設けられています。
案件締め日を1日でも過ぎてしまうと、自動的に翌月の申請に回されてしまいます。
※滋賀県では転用面積が3,000㎡を超えると、滋賀県の諮問案件となるので、もう数日許可が下りる期間が伸びることもあります。

何度でも言いますが、本当に事前調査が大切です。
いきなり書類を準備して申請を行うことがないようにしましょう。
事前調査の時は、「土地登記」「公図」「位置図」の3点は最低限準備して臨むようにしましょう。
当たり前ですが、手ぶらはNGです。窓口で君は何をしに来たの?という顔をされますよ!
許可不要で転用できるケースとリスク

一部の農地転用は、条件を満たせば許可不要で行える場合があります。
しかし、判断を誤れば農地法違反となり、罰則や原状回復命令の対象になるリスクがあります。
ここでは、許可不要とされる代表的なケースを一覧で整理し、誤った判断によるリスクやトラブル事例も紹介します。
安全に土地活用を進めるための注意点を解説します。
許可不要のケース一覧(農地法適用外など)
滋賀県で許可不要とされる農地転用のケースは限られています。代表的なものは以下の通りです。
- 地目が既に宅地や雑種地である場合
登記簿上の地目が農地ではなく宅地・雑種地の場合、農地法の転用許可は不要です。ただし、現況が農地として利用されている場合は例外で、許可が必要になることもあります。 - 農地法適用外の事業
国や自治体が公共事業として行う道路・河川整備、学校建設などは農地法の適用外となります。 - 一時的な転用で農業委員会が承認した場合
農地法第4条・第5条の許可ではなく、農業委員会の届出のみで可能なケースがあります。例えば、農地を一時的に資材置場として使用し、使用後は農地に復元する計画などです。 - 既に転用許可を得ており、用途変更がない場合
過去に許可を得た用途のまま使用を続ける場合、再度の許可は不要です。
滋賀県では、許可不要の判断は非常に慎重に行われます。
たとえば、長浜市で登記簿上は雑種地だった土地が、現況では水田として使用されていたため、農地法の許可が必要とされた事例があります。
許可不要かどうかの判断は、登記簿・現況・用途計画の3つを総合的に見て行う必要があり、自己判断は非常に危険です。

自分で許可不要なケースを紹介しておいて、こんな事を言うのもアレなのですが、
基本的に申請はしなければならない、とお考え下さい。
許可が不要で転用できるケースは非常に稀なケースなので、滅多にそんなケースに出くわすことがありません。
許可なしで転用した場合の罰則と対応
滋賀県で農地を無許可で転用した場合、農地法違反として厳しい処分が下される可能性があります。
主なリスクは以下の通りです。
- 原状回復命令
農地に戻すよう行政から命令が出され、工事費や撤去費用が自己負担となります。 - 刑事罰(懲役または罰金)
農地法違反は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
法人の場合はさらに罰金額が引き上げられます。 - 行政との信頼関係の損失
無許可転用の履歴が残ると、将来の申請審査が厳しくなる傾向があります。
滋賀県では、無許可転用に対して非常に厳格な姿勢を取っており、農業委員会による現地調査が定期的に行われています。
違反が発覚した場合、是正命令に従わないと、罰則適用や強制執行となることもあります。

農業委員の方から聞いた話なのですが、
ある業者さんが、いい加減に申請手続きを進め、是正指導を受けたにも関わらずそのまま放置して、別の申請案件を持ち込んできた、と愚痴を言っておられました。
前の案件をきちんと対応するまで別の案件を受け付けることはできない、と書類を返したそうです。
信頼関係が崩れたので、この業者さんが今後農地転用の申請を行うのは中々大変でしょうね…
滋賀県での農地転用実務の特徴と注意点

滋賀県での農地転用は、琵琶湖や周辺環境の保全、農業振興の観点から全国的にも厳しい基準が適用されます。
特に市街化調整区域での住宅建築は分家住宅などの例外要件を満たさない限り認められません。
ここでは、滋賀県特有の審査傾向や独自基準、許可取得をスムーズに進めるための実務ポイントを、過去の事例を交えて詳しく解説します。
滋賀県の審査傾向と独自基準
滋賀県における農地転用の審査は、全国的に見ても比較的厳格な部類に入ります。
最大の理由は、琵琶湖とその流域の環境保全を最優先に考える行政方針と、農業振興を重視する地域性にあります。
特に琵琶湖周辺では、景観条例や水質保全条例など複数の規制が重なり、農地転用許可の判断に影響を与えます。
市街化調整区域では、都市計画法第34条の例外規定に該当しない限り、住宅建築や事業用施設の建設は認められません。
この例外規定の中でも、もっとも利用されるのが「分家住宅要件」です。
これは、農家の子や孫が独立して住む住宅を建てる場合に限り、一定条件のもとで許可される制度です。
ただし、この分家住宅要件も、
- 本家から一定距離内であること(自治体によって500m〜1km程度の範囲指定)
- 建築希望者が農業に従事している、または将来も従事する見込みがあること
- 宅地化によって農業振興に支障がないこと
といった条件を満たす必要があります。
また、滋賀県では、単に農地法の要件を満たしていても、周辺農地の連続性や景観への影響を理由に不許可となる事例があります。
特に琵琶湖の湖岸や主要観光地付近では、景観形成区域や地区計画が設定されており、建築物の高さ制限や外観デザインの規制が加わります。
これらは都市計画法や景観条例に基づくもので、農地転用許可とは別に審査されるため、事前の総合的な確認が欠かせません。
分家住宅の申請を行った事例において、農業委員会の段階では許可見込みとされていたものが、景観条例による外観制限に抵触する可能性を指摘され、設計変更を余儀なくされたケースがありました。
このように、滋賀県の審査は複合的な要素を考慮して行われるため、「農地法だけクリアすれば大丈夫」という考えは危険です。
さらに、農地以外への転用用途が資材置場や太陽光発電である場合、景観や洪水時の影響、周辺農業への影響を理由に許可が下りないこともあります。
特に太陽光発電は近年、滋賀県では景観保護の観点から厳しい制限が設けられており、パネルの配置や色調、周辺の緑化対策などを詳細に求められることがあります。
総じて滋賀県では、農地法・関係諸法令の2つの観点をすべて満たす計画であることが、農地転用許可取得の前提条件です。
計画段階からこれらを踏まえて準備することで、申請のスムーズ化と不許可リスクの回避につながります。
スムーズに許可を取るための実務ポイント
市街化調整区域で農地転用の許可を得るには、法律の条件を満たすだけでなく、行政や周辺住民との調整も含めた総合的な準備が不可欠です。
特に以下の3つのポイントを押さえることで、審査期間の短縮や不許可リスクの低減が期待できます。
1. 事前協議で行政と認識を揃える
申請前に農業委員会や関係部署と複数回面談し、計画内容の適否を確認します。
この段階で用途や立地条件に懸念点があれば修正できるため、後の差し戻しを防げます。
事前協議時に簡易な位置図や利用計画書を提示すると具体的な指摘を受けやすく、結果として申請の精度が高まります。
弊所でもすべての案件で事前協議を行い、許可取得率の向上につなげています。
お陰様で、申請後に不許可となったケースは今のところありません。
2. 添付図面・用途計画を具体的に作成する
審査では、転用後の土地利用が具体的かつ現実的であるか(実効性があるのか)が重視されます。
配置図や断面図、舗装仕様などを詳細に作成し、必要に応じてカラー図面や完成イメージを添付します。
これにより審査担当者が計画を正確にイメージでき、判断が迅速になります。
特に資材置場や太陽光発電の場合は、周辺との高低差や排水計画も明記すると好印象です。
3. 近隣住民への説明を事前に行う
調整区域では、計画が周辺の生活環境や農業に影響する可能性があるため、住民の理解が重要です。
説明不足による苦情や反対意見は、審査の遅延や不許可につながることもあります。
事前に計画概要を説明し、質問や懸念点を整理しておくことで、申請時に「地域との合意形成が図られている」と評価されます。
また、条例手続きの中で、住民説明会の開催が要件となっている場合もあります。
まとめ
市街化調整区域の農地転用は、都市計画法と農地法の両面から規制されており、許可条件も厳格です。
しかし、条件を正確に把握し、計画を練れば許可は不可能ではありません。
許可の可否は農地の区分や用途計画次第で大きく変わります。
滋賀県では特に景観・農業振興の観点からの審査が厳しいため、事前相談と計画の具体化が不可欠です。
にしの行政書士事務所では、初回相談から事前協議、書類作成、まで一貫して対応し、スムーズな許可取得をサポートしています。
農地転用を検討している方は、是非弊所にご相談頂ければ、と存じます。