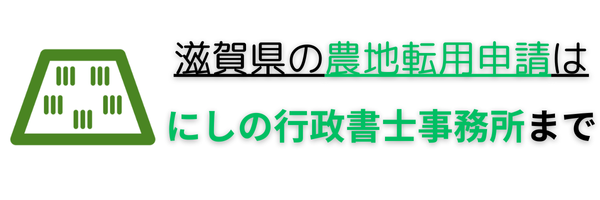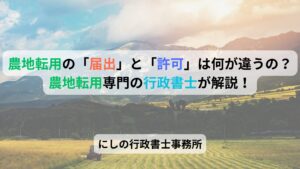地目が山林なのに農地転用が必要!?田畑でなくても農地転用が必要な場合を専門の行政書士が解説!
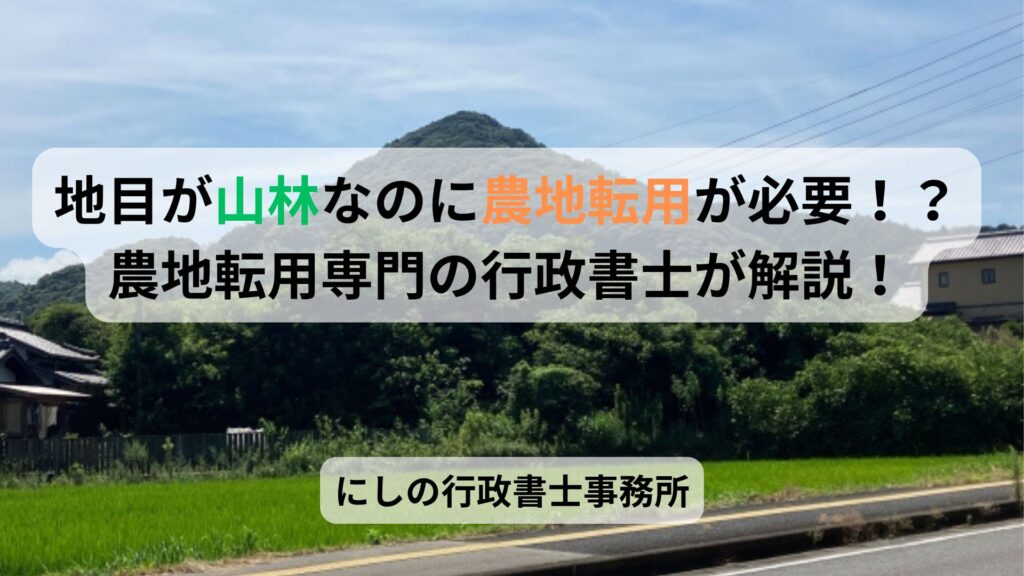
山林を所有している方から、「この土地は農地転用が必要なのか?」というご相談をよくいただきます。
登記簿上の地目が山林でも、実際に畑や田として利用している場合には農地法の規制を受けることがあり、逆に農地が荒れて山林化している場合にも判断が難しくなります。
さらに、固定資産税や相続税評価といった税制の違い、転用にかかる費用や工事内容も気になるポイントです。
本記事では、滋賀県で農地転用に多数携わってきた行政書士の立場から、山林と農地転用の関係を徹底的に解説します。
山林と農地転用の基礎知識

山林と農地は登記上の地目だけでなく、現況の利用状況によっても扱いが変わります。
ここでは、地目「山林」と農地の違い、そして農地転用が必要になるケースを詳しく見ていきましょう。
地目「山林」と農地(田・畑)の違いとは?
土地には「地目(ちもく)」という区分があり、法務局の登記簿上に明記されています。
これはその土地が主としてどのように利用されているかを示すもので、宅地・田・畑・山林・雑種地など20種類以上に分類されます。
地目は課税や規制の対象を判断する基礎資料となるため、土地活用を考える上で非常に重要です。
山林の定義
「山林」とは、樹木の生育を目的とした土地を指します。
木材の生産が主目的である場合はもちろん、経済的な利用がされていなくても樹木が自然に生育している土地は「山林」として扱われることがあります。
また、山林には「保安林」など特別な指定を受けているものもあり、この場合はさらに森林法の規制を受けます。
農地の定義
一方で「農地」は、耕作を目的として利用される土地を指し、米や野菜など農作物の生産を目的としています。
農地法第2条では「耕作の目的に供される土地」を農地と定義し、登記地目にかかわらず、現況が農業利用されていれば農地とみなされます。
これが「現況主義」と呼ばれる考え方です。
登記と現況の不一致問題
実務上よくあるのが「登記簿上の地目」と「現況」が一致していないケースです。
例えば、登記は山林のままになっている土地を畑として利用している場合、実態は農地であるため農地法の規制対象となります。
逆に、登記は農地でも長年放置されて樹木が繁茂している場合、行政は「農地としての機能が残っているか」を調査し、場合によっては依然として農地と判断することもあります。
税制・規制上の違い
農地と山林は課税や規制面でも大きな違いがあります。
農地は食料供給を守る観点から農地法によって厳格に守られており、転用する際には必ず農地転用許可が必要です。
固定資産税についても農地は軽減措置があり、税負担は低くなります。
一方、山林は農地法の対象外であり、主に森林法や都市計画法の影響を受けます。
固定資産税評価は宅地より低いものの、農地よりは高くなる場合もあります。
表で整理:山林と農地の違い
| 項目 | 山林 | 農地 |
| 登記地目の定義 | 樹木の育成を目的とする土地 | 耕作を目的とする土地 |
| 判断基準 | 登記上「山林」:現況に樹木 | 登記上「田・畑」or現況が農業利用 |
| 主な規制 | 森林法・土地計画法 | 農地法 |
| 固定資産税 | 宅地より安い | 更に低い(軽減措置あり) |
| 相続税 | 山林評価方式で算定 | 農地評価(特例あり) |
滋賀県での実例
滋賀県内でも「登記は山林なのに畑として使っている」「農地が荒れて山林のようになっている」といった相談が多く寄せられます。
農業委員会では、登記ではなく「現況」で判断するのが基本方針(=現況主義)です。
したがって、地目が山林であっても畑として耕作していれば農地扱いになり、転用する場合は農地転用が必要になります。
当事務所でも、まず現地の状況を確認し、写真や航空写真を添えて農業委員会に事前相談することで、誤解なくスムーズに手続きを進めています。
山林で農地転用が必要になるケース
山林そのものは農地法の対象外ですが、現況が農地の場合には農地転用が必要です。
ここでは、具体的にどのようなケースで転用が必要になるのかを解説します。
ケース1:登記は山林、現況は畑
最も多いのは「登記地目が山林なのに、実際には畑として耕作している」というケースです。
山林地目のまま放置していると、「農地ではないから転用不要」と誤解しがちですが、現況が農地であれば農地法の規制を受けます。
宅地化や駐車場化を進める場合には農地転用許可が必要です。
ケース2:農地が荒れて山林化
逆に登記は農地のままでも、長年放置されて雑木林のようになっているケースがあります。
この場合も「地目=農地」である以上、転用する際には農地転用許可が必要です。
非農地証明を取得できれば農地法の規制を回避できる可能性がありますが、発行には厳格な現地調査が行われるため、必ずしも認められるわけではありません。
ケース3:相続や売買の場面
相続で土地を取得した際、ケース1のような問題が発生することがあります。
売買の際にも同様で、買主が住宅を建てようとした場合、地目が山林でも現況が農地なら、農地転用許可が必要となることがあります。
特に相続した土地は、土地について良く分かっていないことが多いので、注意が必要です。
確認を怠ると契約が無効になったり、工事が中断されるリスクがあるため要注意です。
滋賀県の傾向
滋賀県では特に市街化調整区域に多くの農地・山林が存在しており、現況判断が厳しく行われる傾向にあります。
農業委員会では「農地か否か」を現地で細かく確認し、少しでも耕作可能性があると判断されれば当該土地が「農地」だと判断されます。
実際に当事務所に相談して下さった方も、「山林だから大丈夫」と思い込んでいた地主が実際には農地転用許可を求められた、と仰っておられた方がいらっしゃいました。
そのため、必ず事前に確認を行うことが不可欠です。
山林と農地の税金の違い

山林と農地は利用目的や法規制だけでなく、税金の取り扱いにも大きな違いがあります。
固定資産税・相続税評価・税制優遇の有無などを理解しておくことで、農地転用を検討する際の判断材料となります。
山林と農地の固定資産税の違い
土地を所有する際に必ず発生するのが「固定資産税」です。
この税額は土地の評価額に基づいて計算されますが、山林と農地では評価方法や課税水準に大きな違いがあります。
固定資産税の基本
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地所有者に対して課税され、評価額×1.4%(標準税率)が税額の基礎となります。
ただし、土地の種類によって評価額の算出方法が異なり、農地・山林・宅地でそれぞれ大きな差が出ます。
山林の課税評価
山林は宅地や農地と比べて市場流通性が低く、収益性も限られているため、評価額は比較的低く設定されます。
ただし「山林評価」と呼ばれる独自の方法で評価されるため、単純に面積だけでなく林齢(木の年齢)、立地条件(傾斜、交通条件)、木材需要なども考慮されます。
結果として、山間部の急斜面の山林は税負担が極めて軽い場合があります。
農地の課税評価
農地は、農業振興のために税制上の優遇措置がとられています。
特に「純農地」と呼ばれる農業適地は評価額が低く抑えられており、固定資産税負担も小さいのが特徴です。
また、市街地農地は「宅地並み評価」となるため、都市近郊の農地では負担が大きくなるケースもあります。
転用後の影響
農地を転用して宅地や雑種地にすると、固定資産税評価額は大きく上昇します。
特に、宅地化した場合は「路線価」や「地価公示」に基づく評価となるため、農地の時と比べて数倍に跳ね上がることも珍しくありません。
地主にとっては大きな負担増になるため、農地転用を決断する際には税負担の増加をシミュレーションする必要があります。
実際にご依頼頂いた案件では、農地を太陽光発電や駐車場に転用した後、固定資産税が年間数万円から数十万円に増加したケースがありました。
山林と農地の相続税評価
相続の場面でも、山林と農地は評価方法や税制優遇で大きく異なります。
特に「納税猶予制度」の有無が大きなポイントです。
山林の相続税評価
山林の評価は「山林評価」と呼ばれる独自の算定方式で行われます。
木材の収益性や林地の条件を基準に計算され、一般的に宅地よりも低めに評価されます。
ただし、山林には農地のような「相続税の納税猶予制度」が存在しないため、課税評価がそのまま相続税に直結します。
相続人に農業従事者がいない場合でも減免措置がない点は注意が必要です。
農地の相続税評価
農地は、区分ごとに評価方法が異なります。
- 純農地・中間農地:農業利用を前提とした農地。税額が低く評価される
- 市街地農地:宅地並み評価で高額になりやすい
さらに大きな違いは「農地の納税猶予制度」があることです。
一定の条件を満たせば、相続した農地に対する相続税の納税が猶予され、相続人が農業を継続する限り納税を免れることも可能です。
この特例は農業継続を守るための強力な制度であり、山林には存在しません。
相続時の戦略
この違いから、地主や相続人は「農地のまま相続するか」「山林にしておくか」で大きく税額が変わります。
農業を継ぐ後継者がいる場合は農地のままの方が有利ですが、後継者がいない場合には山林扱いにした方が良いケースもあります。

西野
本コラムで解説している税金の話は、あくまで一般論です。
個々の事情により異なることがありますので、気になる方は税理士に相談するか又は役所の税務課に尋ねてみるようにしましょう。
行政書士に税金のご相談はできませんので、予めご了承ください。
山林の農地転用にかかる費用

山林を農地転用する際には、手続きにかかる費用と実際の整地・造成といった工事費用が発生します。
ここを正しく把握していないと、想定以上のコスト負担に驚くことになります。
農地転用手続きにかかる費用
農地転用を進めるにあたり、まず必要となるのが行政手続きです。
費用の内訳は大きく分けて「行政書士等への依頼費用」「添付資料の準備費用」に分かれます。
行政書士報酬
農地転用の許可申請は、一般の方が自分でやることも可能ですが、専門知識が必要なため行政書士に依頼するのが一般的です。
報酬の相場は規模や難易度によって変動します。
- 小規模(駐車場や資材置場など数十坪規模):5〜10万円程度
- 中規模(住宅建築や事業所建設):10〜20万円程度
- 大規模(太陽光発電や倉庫建設など数千㎡以上):30万円以上
滋賀県でも、転用予定地よっては農振除外や都市計画法29条の開発許可が絡むため、報酬が高めになることがあります。
当事務所では「一律いくら」というのではなく、事前調査の結果と案件の複雑さに応じて見積もりを提示する方式をとっています。
添付資料の準備費用
農地転用許可申請には、登記簿謄本、位置図、配置図、平面図、排水計画図などの添付が必要です。
図面関係は土地家屋調査士や建築士に依頼する場合も多く、数万円~数十万円単位の費用がかかります。
実務上の注意点
その他にも案件ごとに費用が掛かる場合があります。
例えば、転用予定地が土地改良区に属している(受益地)場合、農地転用をしようとすると、土地改良区の手続きを先に済ませておく必要があります。
受益地から除外する場合、転用決済金を土地改良区に支払う必要があります。
転用決済金は平米あたりいくら、と決まっているので転用面積が大きい場合、転用決済金が数十万円になることがあります。
整地・造成など実際の工事費用
農地転用で見落としがちなのが「実際の土地整備にかかる費用」です。
特に山林を転用する場合は伐採や伐根などの工事が必要になるため、農地からの転用よりも費用が高額になる傾向があります。
伐採・伐根費用
山林には樹木や雑木が生い茂っているため、まず伐採・伐根工事が必要です。
費用は規模によって変動しますが、100坪で30〜50万円程度が目安です。大木が多い場合はさらに高額になります。
伐採した木材の処分費用も見込んでおく必要があります。
整地・造成費用
伐採後は整地・造成を行います。
土砂の搬出や盛土、転圧作業などを経て、建築や駐車場に適した地盤を整えます。
こちらは100坪で50〜100万円程度かかることが多く、傾斜地の場合は法面工事や擁壁工事が追加で必要となり、数百万円規模になることもあります。
排水・地盤改良
転用する土地は雨水処理や地盤強化が不可欠です。
特に滋賀県は雨が多く、排水処理を怠ると隣接地への被害につながるため、農業委員会の審査でも排水計画は重要視されます。
側溝設置や浸透桝、地盤改良費用を含めると数十万円以上の追加費用となります。
工事費用の合計目安
以上を合計すると、100坪程度の山林を農地転用して駐車場にする場合でも、伐採・整地・排水で150〜250万円程度かかることが多いです。
宅地化を伴う場合はさらに造成費用や上下水道引込費用が加わり、300〜500万円程度になることもあります。
もちろん、転用目的によって掛かる費用は様々なので、あくまで上記金額は参考程度にお考え下さい。
農地転用の手続きと流れ

山林が現況農地として利用されている場合、農地転用の許可が必要です。
ここでは、許可が必要な場合と、非農地証明で済む場合の2つの流れを詳しく解説します。
農地転用許可が必要な場合の流れ
繰り返しになりますが、山林であっても現況が農地である場合には、農地転用の許可を取得しなければなりません。
ここでは、その具体的な流れを整理します。
① 事前相談
何はともあれまずは、管轄の農業委員会への事前相談です。
農業委員会は「その土地が農地に該当するかどうか」「転用が許可される可能性があるか」を判断する窓口です。
事前相談では、登記簿謄本、公図、現況写真を持参し、土地の状況や利用目的を伝えます。必要書類に関する不明点も一緒に確認しておくと良いです。
当事務所でも、必ず事前相談を行い、リスクを最小限に抑えています。
② 農振除外(必要な場合)
その土地が農業振興地域(青地)に含まれている場合は、まず農振除外を申請しなければなりません。
青地か否かは農業委員会事務局ではなく、農政課(役所によっては「農業振興課」)で確認できます。
農振除外は年に1〜2回しか受け付けていない市町が多く、受付期間を逃すと申請が数ヶ月〜1年先送りになることもあります。
除外には公益性のある事業や周辺農地への影響の少なさが求められます。
※青字の転用は本当に難易度が高いです。事業地としての活用見込みは絶望的なので、避けた方が無難です。
③ 農地転用許可申請(農地法第4条・5条)
農振除外を経た後、農地法に基づく転用申請を行います。
- 4条申請:自己所有の農地を自ら転用する場合
- 5条申請:農地を他人に売却・賃貸して転用する場合
申請書には、土地の位置図、平面図、配置図、排水計画図、資金計画書などを添付します。
市町毎に書類が微妙に違ったり、要求される水準が異なるので、きちんと確認しておくようにしましょう。
農業委員会が受理した後、審査は県知事または農業委員会の権限で行われます。
④ 審査のポイント
審査では、以下の観点が特に重視されます。
- 周辺農地への悪影響がないか
- 土地利用計画が妥当か(排水・進入路が確保されているか)
滋賀県では特に「排水計画」が重視される傾向があり、申請図面に雨水処理の方法を明示することを求められることが多いです。
⑤ 許可・登記変更
許可が下りたら、法務局で地目変更登記を行い、正式に農地以外の利用が可能となります。
地目の変更申請のためには、現に土地の現況が変わっている必要がありますので、現況を変えてから申請する必要があります。
ここまでの手続きには数ヶ月かかることもあり、時間的余裕を持った計画が重要です。
非農地証明で済む場合の流れ
一方、農地法の許可を経ずに済むケースもあります。それが「非農地証明」です。
① 非農地証明とは?
非農地証明とは、その土地が農地としての利用実態を失っていることを農業委員会が証明する書類です。
これを取得すれば、農地法の規制を受けずに地目変更登記が可能になります。
② 申請手続き
申請には、登記簿、公図、現況写真、場合によっては航空写真などを添付します。
農業委員会が現地調査を行い、農地として利用できない状態と判断されれば証明が発行されます。
③ 認められる基準
非農地証明が認められるかどうかは厳格に判断されます。
- 長年耕作が行われていない
- 樹木が繁茂し、農地としての利用が不可能
- 用排水施設が撤去されている
ただし、雑草が生えているだけでは「まだ農地利用可能」と判断されることが多く、証明は認められません。
過去にも「見た目は山林のようでも、農地として利用可能」とされ、非農地証明が却下されるケースがありました。
④ メリットとデメリット
非農地証明を取得できれば、農地転用許可のように数ヶ月待つ必要がなく、比較的早く登記変更が可能になります。
しかし、証明が認められるケースは限られており、申請が通らなければ改めて農地転用許可を取らなければなりません。
山林の無断転用のリスクと注意点

山林を農地転用する際には、法令違反や追加規制、地域との調整不足など、見落とされがちなリスクがあります。
必要な手続きを事前に確認し、対応することで違反を犯さず、スムーズに転用することが可能です。
許可を得ずに転用した場合のリスク
農地転用をせずに土地利用を変更した場合、「農地法違反」となり、行政処分の対象になることです。
無断転用の罰則
農地法第64条では、無断で農地を転用した者に対して「原状回復命令」や「罰金刑」が定められています。
原状回復命令が出された場合、造成した土地や建築した建物を撤去して農地に戻す必要があり、経済的損失は非常に大きなものになります。
例えば、駐車場としてアスファルト舗装した場合でも、撤去を求められた例があります。
詳細はコチラをご覧ください。
将来の売却・融資への影響
無断転用の土地は、不動産取引においても大きなマイナス要素になります。
金融機関は農地法違反状態の土地には融資を行わないことが一般的であり、買主が住宅ローンを組めないために売買契約が破談することもあります。
また、不動産登記上は農地のままであるため、権利関係の整合性も取れなくなります。
社会的信用の低下
地域住民や行政からの信頼を失うことも大きなリスクです。
農地法違反を起こした地主や事業者は「法令を守らない相手」と見なされ、今後の土地利用計画や他の申請でも不利になることがあります。
特に滋賀県のように農業委員会と地域社会の関わりが強い地域では、信用を失うと回復が難しくなります。
滋賀県でのよくある注意点
滋賀県で山林の農地転用を検討する際には、農地法以外にも複数の法令や地域特有の事情が絡み合うことが多くあります。
市街化調整区域の規制
滋賀県内では、広範囲に渡って市街化調整区域が形成されています。
この区域では原則として開発行為や建築が制限されているため、農地転用許可を得ても都市計画法の開発許可が下りなければ利用できません。
例えば、資材置場や倉庫を建てる場合には、都市計画課と農業委員会の両方に申請が必要になります。
保安林指定の有無
山林には「保安林」に指定されているケースがあり、この場合は森林法の規制を受けます。
保安林は水源涵養や土砂災害防止のために重要視されており、解除や転用には農地法以上に厳格な手続きが必要です。
滋賀県北部の山間部では、保安林指定を理由に転用が認められないことも珍しくありません。
排水計画の重要性
滋賀県は琵琶湖を中心とした水系環境を守るため、排水計画に特に厳しい基準を設けています。
農地転用においても、雨水や生活排水が隣接地や河川に悪影響を及ぼさないことを証明する必要があります。
農業委員会の審査でも図面に排水計画を明示することは必須であり、曖昧な計画では補正を命じられ手続きがストップしてしまいます。
山林農地転用の実例とケーススタディ

実際の相談や事例を通じて、山林と農地転用の関係をより具体的に理解できます。
ここでは典型的な2つのケースを取り上げ、手続きの流れや注意点を詳しく解説します。
遊休農地が山林化したケース
背景
滋賀県某市のある地主の方から、「昔は田んぼとして利用していたが、10年以上放置した結果、雑木や竹が生い茂って山林のようになってしまった土地を駐車場にしたい」という相談が寄せられました。
登記地目は「田」のままですが、現況は完全に山林化しており、相談者様は「山林だから農地転用は不要」と考えていました。
課題
実際には地目が農地であるため、農地法の規制を受け、農地転用許可が必要でした。
しかし、相談者様は「農地として使えないのに、なぜ農地扱いなのか」と納得できないご様子でしたが…
手続きの流れ
- 現地調査:当事務所が現地を確認し、雑木や竹が密生して農地としての機能が失われている状況を記録。
- 農業委員会への相談:現況写真を添えて説明したところ、「非農地証明は難しいが、転用許可なら可能」と回答。
- 転用申請の準備:配置図や排水計画を整え、駐車場としての利用計画を明確化。
まとめ
この事例から分かるのは、「地目が農地のままでは、現況が山林であっても農地法の規制を回避できない」ということです。
思い込みで無断造成してしまえば、罰則や原状回復命令のリスクもありました。
当事務所にご相談いただいたことで、正しい手続きを踏んだからこそスムーズに許可が得られたケースです。
山林地目だが畑利用していたケース
背景
別の事例では、登記上は「山林」となっている土地を、長年畑として利用していた方からの相談がありました。
相談者様は土地を売却して住宅用地として活用したいと考えていましたが、不動産会社から「現況が農地なら農地転用が必要」と指摘され、当事務所に相談されました。
課題
相談者様としては「登記地目が山林なのだから農地ではない」と思い込んでおられました。
しかし、農業委員会に照会すると、現況が畑であるため「農地」として扱われ、農地転用許可を取らない限り売却や宅地化は認められない状況でした。
手続きの流れ
- 農業委員会への事前相談:現況が農地であることを前提に、売却のための農地転用許可が必要と説明を受ける。
- 農地法第5条申請:地主が売却し、買主が住宅を建てる計画であるため、5条申請を選択。
- 必要資料の準備:位置図、平面図、排水計画、売買契約書の案を添付。
- 審査と許可:周辺農地への影響がないこと、宅地として公益性があることを説明し、許可を取得。
- 地目変更登記:売却に合わせて登記を宅地へ変更し、買主が住宅建築に着手。
まとめ
このケースから分かるのは「登記地目ではなく現況が重視される」ということです。
山林地目だからといって農地法の規制を回避できるわけではありません。現況農地であれば、必ず転用許可が必要になります。
コラムのまとめ
山林と農地は登記上の地目も規制法令も異なりますが、現況利用によっては農地転用が必要となります。
固定資産税や相続税の違い、転用に伴う工事費用も軽視できません。
特に滋賀県では、市街化調整区域や保安林など他法令との重複も多く、慎重な対応が求められます。
にしの行政書士事務所では、山林や農地に関する多様な案件をサポートしてきました。
農振除外や非農地証明、農地転用許可、地目変更登記、さらには行政との協議まで一貫して対応可能です。
山林に関する農地転用を検討されている方は、ぜひ早期にご相談ください。
\⇩まずは無料相談・お見積りから!⇩/
〈お気軽にご相談ください〉
※LINEからのお問合せ・ご相談がスムーズに進むのでお勧めです。